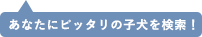アメリカンコッカースパニエルは、明るく陽気、
人懐っこく甘えん坊で小さなお子様や高齢者の方にも
飼いやすい犬種です。
しかし、優雅な外見からは想像もつかないほど、
非常にタフでスタミナがあり遊ぶことが大好きな犬種です。
室内での自由遊び以外にも、朝・晩 毎日約30分ずつくらいの
お散歩をするようにしましょう。
ドッグランなどで思いきり走らせてあげるのもいいですね。
ただし、激しい運動をさせるのは、体が出来上がる生後6ヶ月くらいまでは
控えるようにしましょう。
また、お散歩の注意点として、真夏の炎天下でのお散歩は、絶対に避けるようにしてください。
熱せられたアスファルトにより足の裏をやけどしてしまったり、
熱中症で最悪、命を落としてしまう危険性もあります。
真夏は、早朝や日没後の涼しい時間帯にお散歩に行くようにしましょう。
屋外飼育もできますが、もともと社交的な犬種なので、精神的に弱ってしまう可能性があります。
そういった面でも室内飼育をおすすめします。
アメリカンコッカースパニエルは覚えが早く、注意力や観察力も高く、
とっても頭の良い犬種なのでしつけしやすい犬種です。
ただし賢い分、1回でも恐ろしい思いをするとそれがトラウマになり、
集中できなくなることも多いので注意して育てるようにしましょう。
また、仔犬のころ、可愛いからと過保護にし過ぎるとワガママになってしまいますので
注意してくださいね。
 アメリカンコッカースパニエルを飼育する上で、
アメリカンコッカースパニエルを飼育する上で、
トリミングは非常に重要です。
短く刈ったりすることもありますが、毛量が大変多いため
お手入れには十分な時間をかけてあげましょう。
また、けがなどの早期発見やコミュニケーションもかねて、
お手入れをしてあげるようにしてください。
◎ブラッシング・シャンプー
毛量が多く、毛の伸びも早いため、最低でも週に2~3回のブラッシングと
月1回はシャンプーを行うようにしましょう。
しかし、シャンプーはあまり頻繁に行うと、皮膚の乾燥がひどくなります。
汚れが目立つような時は、シャンプーの代わりに蒸しタオルで体を拭いてから、
ブラッシングしてあげるようにしてください。
長い被毛に覆われている足は、ほこりがたまりやすいため、
お散歩から帰ってきたら丁寧に拭いてあげるようにしましょう。
また、子犬の頃から行うようにしていると大きくなってからも
嫌がることなく喜んでやらせてくれますよ。
◎耳のお手入れ
アメリカンコッカースパニエルは垂れ耳であることに加えて毛量が豊富ですので、
耳の中の通気性が悪くなります。
その結果、細菌が繁殖しやすい環境となり、外耳炎などの病気の原因となります。
余分な毛は抜くか、カットするようにして、通気性をよくするように心がけましょう。
また、イヤークリーナーなどを使用して、最低でも、
月に1回は耳掃除をしてあげるようにしましょう。
◎爪のお手入れ
毎日のお散歩でたくさん歩いていれば、アスファルトで削れ、
定期的にトリミングで一緒に切ってもらうぐらいで十分です。
でも、親爪だけは地面に着かないためどんどん伸びてきてしまいます。
親爪があるワンちゃんはトリミングの時以外でも、
伸びていないか確認してあげる必要があります。
犬は爪のなかに神経と血管があり、放っておくと爪と一緒に伸びてきます。
この状態でつめ切りをすると、キャンっと悲鳴をあげ、血も出てきます。
また、つめを伸ばしたままにしておくと、肉球にくい込み、
歩くごとに痛みを感じるようになってしまいます。
慣れないうちは、トリミングの際に一緒に爪もカットしてもらうか、
健康診断兼ねて、動物病院にてカットしてもらうというのも一つの手です。
◎食事管理
アメリカンコッカースパニエルは、
小柄ながら
大変食欲旺盛で、何でもよく食べます。
それゆえ、
太りやすい体質ですので、
しっかりとした食事管理が必要です。
肥満は様々な病気の引き金となりますから、
くれぐれも太らせないように心がけましょう。
これらを意識し、仔犬の時から食事管理をしっかりと行うことが大切です。
アメリカンコッカースパニエルがかかりやすい病気は以外と多くあります。
◎白内障
眼の水晶体が白濁することで視力が低下し、ふらふらと歩いたり段差につまづくなど、
歩行自体がぎこちなくなります。
初期の段階ではさほど支障なく歩行が可能ですが、重症になると失明することもあります。
原因としては、遺伝的要素の強い先天性と、年を重ねたことによる後天性があります。
一番多いのが後天性の「老年性白内障」です。
糖尿病による併発の場合もあります。
(対策)
正直なところ、この病気の予防法はありません。
ですが、早い段階で気づけば点眼薬などで進行を遅らせることが可能です。
また、外科的手術で眼内レンズをいれて視力回復させたり
水晶体を取り除く方法もあります。
いずれにせよ、早期発見・早期治療が非常に大切です。
糖尿病起因の場合は、そちらの治療を始めますが、まずは糖尿病にならないことが先決。
◎緑内障
眼球内部の圧力が高くなることによって、目が強く充血したり、
飛び出したようにみえます。
また、強い痛みがあったり、目の色が赤や緑に見えたりします。
視力が低下して、最悪失明する事もあります。
投薬をつかった内科療法と、投薬での治療は難しい場合に外科的療法が行われます。
(対策)
小型犬に発症しやすい傾向があるようです。
犬は少々見えづらくなっても、通常の生活を送ることが出来るので
飼い主の発見が遅れがちです。
"頭をなでられるのを嫌がる"
"ひどい涙目になっている"
"なんとなく目がにごっている"
などの症状に日頃から注意する事で早期発見・早期治療につながります。
また、6~7歳の高齢期になったら、特別気になる症状がなくても、
定期健診を受けるようにしましょう。
◎膝蓋骨脱臼 (しつがいこつだっきゅう)
小型犬の代表的な病気です。
「膝蓋骨」とはいわゆる"膝のお皿"のことで、膝の伸縮時に靭帯をずらすことなく
スムーズに関節が動くようにしている骨です。
この骨が脱臼してしまうことで、靭帯も機能しなくなり、
足を着くことが出来ないため歩行が困難になります。
原因は先天性と後天性に分けられます。
生後1年以内に手術すれば完治するといわれています。
(対策)
フローリングなどの滑りやすい場所での運動や、急な階段の上り下りなど、
激しすぎる運動は避けるようにしましょう。
◎股関節形成不全
遺伝や後天的な要因によって、股関節が正常に形成されない病気です。
座り方がおかしい・足を引きずる・痛がるなどで歩行に障害が出て、
運動を嫌うようになった場合はこの病気の疑いが高いです。
早ければ4ヶ月頃から症状がでます。
治療は、軽度ならば内科的治療ですが、重度になると外科手術を行います。
手術にもいくつか種類がありますが、特に効果が認められているのは、
人工関節を装着する手術です。
(対策)
遺伝的なものの場合は、親犬にそういった病気を持っていないか調べてから
子犬を迎える準備をすること。
後天性の場合は、肥満により、成長過程の股関節に負担をかけることが主な原因です。
小さい頃からしっかり食事を管理し、栄養過多にならないようにしましょう。
 コッカー飼育上の注意点【 コッカー・ブリーダーズ 】
コッカー飼育上の注意点【 コッカー・ブリーダーズ 】 コッカー飼育上の注意点【 コッカー・ブリーダーズ 】
コッカー飼育上の注意点【 コッカー・ブリーダーズ 】 アメリカンコッカースパニエルは、明るく陽気、
アメリカンコッカースパニエルは、明るく陽気、 アメリカンコッカースパニエルを飼育する上で、
アメリカンコッカースパニエルを飼育する上で、